- 大学の(理工系)実験のレポートを書こうとしている学部生(学部1〜3年生相当)
- 卒業研究の卒論を書こうとしている学部生(学部4年生相当)
この記事では、大学の実験の授業における「レポートの書き方」について解説します。
多くの(主に理工系)大学生が
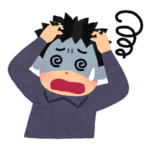
- 実験レポートを毎週提出するのがとてもキツイ!
- どうすれば良いレポートを書けるか分からない!
という悩みを抱えていると思います。
本記事を読むことで
実験の先生に「よく書けているね」と褒めてもらえるような、良いレポートの書き方
を大まかに掴んで頂けると幸いでございます。
また本記事で学んだ内容は、学部4年生とかが行う
卒業研究の卒業論文を書く際にも役に立つはずです。
本記事を執筆している、私トーマは、物理学者として勤務しています。
そんな私が分かりやすく解説いたします。
なお、大学院生以上の方向けに「論文の読み方」に関しても解説しております。
併せてご覧いただけると幸いでございます。
実験目的
書く際のポイント

実験目的なんて、1~2行で適当に書けばいいでしょ?
なんなら、貰ったテキストに書いてある「目的」の部分を丸写しすれば良いじゃん。
と思う人がいるかもしれません。
確かに実験目的を書くこと自体は、ほぼテキストの丸写しになってしまうことも多いですが「実験レポートで最重要なのは実験目的である」と言っても過言ではありません。
序論、実験方法、実験結果、考察は、全て「実験目的と整合する」ように書かれていなくてはいけないのです。
実験目的ときちんと整合するように、序論などを書く方法は、後の節で説明します。
目的を書く際に必要なことは
実験を通して
- 何を明らかにしようとしているのか?
- 何を理解しようとしているのか?
を明示する。
ことです。
何か明らかになっていない(理解できていない)ことがあるから、実験で明らかにしようとしているのです。
学生実験ではすで既に答えの分かりきっている問題を扱いますが、この書き方を意識しておくと、4年生や大学院での研究室での研究で、未知の問題を扱うときに役に立ちます。
テンプレート
〇〇を用いた実験により、××や△△などを観測することで
〇〇に特有の現象を深く理解する。
上記のテンプレートに関して
- 〇〇:実験の対象
- ××や△△:実験の対象(〇〇)に関して観測される現象
を当てはめるといいでしょう。
上記の例文では「実験の対象(〇〇)に特有の現象」を理解しようとしていることが分かります。
序論
書く際のポイント

序論に何を書けばいのか分からないよ
序論は、多くの学生さんが悩むパートだと思います。
序論を書く際の大原則は
なぜこの実験を行う意味があるのか?
(=なぜ実験目的を達成する意味があるのか?)
が伝わるように書く。
ことです。
これがストレートに伝わるためには、以下のような構成にして書くといいでしょう
(1項目に対して1段落を目安にすると良い)
- 実験の対象(今回ならコロイド)とは何か?
(1∼ 2 文程度で簡単に解説) - 実験の対象は、自分たちの身の回りでどのように応用されているか?
or 何が重要なのか? - 実験対象に関して、これまでどのようなことが分かってきたのか?
(先行研究などに言及) - 実験対象を調べる事の何が興味深いのか?
or 現在のところ何が分かっていないのか?
上記の内容に関して、自力で分からなかったらネットや本で調べましょう。
本などの記述を使用する場合には、参考文献の引用を忘れないようにしましょう。
上4 つ全てを書くことができなくとも、必要な部分だけでも書きましょう。
実験方法
書く際のポイント
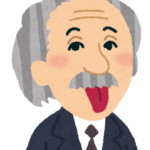
その日の実験で、実際に行った工程を、手順通りに過不足なく書きなさい
先生からも口酸っぱく言われていると思いますが、まさにその通りです。
「実験方法」のパートは、この指示に忠実に従って下さい。
実験方法を書く際の主な注意点として
- 過去形で書く
(これも先生に言われましたよね?) - 材料や試料の正式名称を書く
(メーカー名も書いた方がいいかも?) - 装置や器具の正式名称を書く
(例:ビーカー、メスフラスコなど) - 実験条件をはっきり書く
(温度、溶液の濃度、容量、時間、回数など)
があります。
その他にも、先生からの指示にきっちり従って書きましょう。
逆に、上記の注意を守っていれば十分ですし、自分が行なった手順を機械的に辿ればいいだけなので、難しくないパートだと思います。
結果
書く際のポイント
実験を通して、数値や画像データを得たと思います。
「結果」のパートでは、その得られたデータの説明をしていきます。
その際には
- 結果ごとに小見出しを付ける
(「結果1:〇〇」「結果2:××」みたいな感じで) - 何を目的にどのような操作を行なったのかを、簡単に書く
- 「どのような結果が得られたのか?」「その結果の特徴は何か?」を書く
- 最後に結果をまとめると分かりやすいかも
という方法で書くと分かりやすい説明になるでしょう。
ただ、これだけだと抽象的すぎて分かりにくいと思いますので、以下のテンプレートも交えて理解して頂けると幸いでございます。
テンプレート
結果1:〇〇の××(小見出し)
△△を検証するために、〇〇の観察を行い、∗ ∗ の解析を行なった。(目的と操作の概略)
その結果、図1に示すように、Aでは ⬜︎⬜︎ の値、Bでは ⬛︎⬛︎ の値を取り、AよりBで値が増大していた。
また図2に示すように、Cの場合では××が観測され、∗ ∗ の値はAとBでの値よりも有意に低くなっていた。(結果とその特徴)
これらの結果により、〇〇は◇◇で××であることが明らかとなった。(結果のまとめ)
上記のテンプレートを基に、実際に行った実験に応じてアレンジして下さい。
考察
書く際のポイント
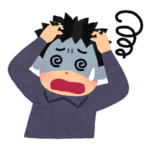
「考察」って何だよ!
何を書けばいのか分からないよ!
多分レポートで、一番難しいのが考察パートだと思います。
何を書けばいいのか分からない人が多いでしょう。
考察パートは
今回の実験結果は
仮説や実験目的と照らし合わせてどうだったか?
を書きましょう。
その際に、以下のポイントを意識すると書きやすいでしょう。
- 実験結果は科学的に信頼できるか?
(実験機器の性能や実験操作でどのくらいの数値誤差が出たか?、画像データは信頼できるか?など) - 実験手順などに問題はなかったか?あるいはその改善点は?
(実験で特定の操作を行なったこと自体が結果に影響を及ぼしていないか?操作ミスをしていないか?どうすればより良い結果が得られると考えられるか?) - 実験結果がどう解釈できるか?or どういう意味を持つか?
(文献や理論による仮説と合致するか?or 矛盾するか?、仮説を支持するor 否定するのに十分な結果が得られているか?、もし得られていないなら何が足りないのか?など) - 実験結果を解釈してみた結果、実験目的を達成できたと言えるか?否か?
これらの問いに、すぐに答えるのは難しいと思うので、ネットや本などの文献を参考にしましょう。
まとめ
本記事の解説を参考に実験レポートを書くのはもちろん、(もし手に入るなら)他人のレポートを読んでみることをオススメします。
そうすると、良いレポート・悪いレポートの区別がつくと思いますし、良いレポートに出会えたらその文章の構成や書き方が大いに参考になるはずです。

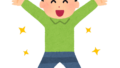
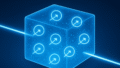
コメント